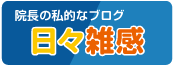ある外食チェーンの社長さんに
インフルエンザ、大丈夫ですか?と聞いたら
「おれが風邪なんかひいたら終わりだよ」とのこと。
外食業界はいま大変みたいですね。
気合が入っているときは風邪をひかないものです。
私はもうすぐ開業7年目ですが
今のところ皆勤賞です。
そんなに体は強いほうではないのですが
自宅で休日、「なんか熱っぽいなー」とか、
職場で「なんだかのどが変」と思った時には
明日の診療のアポイント表を見ます。
そうすると治ります。
風邪をひいてる場合じゃないと
気合が入るわけです。
この事実に気づいてから
この方法を積極的に活用してます。
歯のことで複雑な問題を抱えた患者さんが
遠くから通ってきてくれてますので
治療にあたっての段取りや
応用する技術、方法、材料、道具、必要な準備・環境の整備
説明、費用、患者さん体調、スケジュールとの調整などなど
それらがプラン1、プラン2と・・・
考えることはいくらでもあるわけです。
あと私はもともと物を組み立てたり、
機能を考えたりするのが好きなようで
小さいころから、夜布団に入ると頭の中で
いろんな機械や機能が組みあがってた
ように記憶してます。
で、仕事に体力面でも支えられてる様な感じで
先日こんな言葉を見つけました。
フランスの哲学者でボルテールという人の言葉だそうです。
「仕事は私たちを疲労と邪悪と欲求から守ってくれる。」
確かに、仕事もなく、生産性の低い気合の入らない日々を送っていたら、どうなるでしょう。
まあ誰にもいくつもの役割があり、がんばるのは仕事だけではないとは思いますが。
自分のようなタイプは将来定年後が心配でもありますが
目と手と頭がきっちり働く間はやると思います。
私の師匠だった先生はもう70才近くになりますが
「(歯科用)マイクロスコープがある限り君らには絶対負けん」
と言っています。
確かに素晴らしい仕事をしてます。
社会の高齢化が進んでいますが
技術革新は頭の柔らかい高齢者の
「生涯現役」を実現するのかもしれないと
思いました。
2009年11月17日 00:00