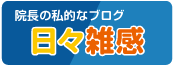パウダーで予防
予防処置のための新しい設備を導入しました。パウダーを吹いて歯垢を飛ばすことで
歯にやさしく、また従来器具の届きにくかったところまで
すっきりきれいにできます。
軽度のステインも同時に取りますので
やるほど、白くつるっとした歯になります。
短時間で歯にやさしく、すっきりと歯垢を取れる
予防処置の「ゲームチェンジャー」になりうる
新しいコンセプトです。
昔から着色を取るエアフローはあったのですが
パウダーや機械の性能に問題があって、
歯肉などにダメージを与える危険性がありました
でも今度の機械には歯肉へのダメージはありません。
そのため、歯と歯茎の境目のプラークまで取れて
つるっつるになります。
プラーク(バイオフィルム)が
古くなって
感染性が増す前に
パウダーですっきり除去してしまう
20数年前に
私の前の職場に歯科機械中堅企業の
エアフローの開発担当者が来たので
「いずれこの時代が来る」
(エアフローでプラークを取る時代)と
さんざん力説させていただいたのですが
時代が来るのに
20数年たってしまい
申し訳ありませんでした…
機械はスイス製です
この分野でも日本は取られてしまいました
世界のサイエンスの流れに乗って
どんどん英語論文でエビデンスを蓄積して
特許をとっていれば
機械やパウダーは日本の得意分野だったでしょうに
スマホでも
アップルのiphoneより前から
シャープの「ザウルス」とかあって
日本のお家芸だったのに
当時アップルは
パワーマック9000シリーズとか
非常に迷走していて
つぶれそうで
ジョブズが現れて
製品ラインナップをすべてリセットして
iMACを出して
ipadをジョブズが実演したときには
「あんな重いものであんなことするかよ」
みたいに笑われて
でもその後iphoneを出して
世界を変えてしまった
ちなみに
パウダーは従来の重炭酸ナトリウムとかではなく
エリスリトールというもので
汚れを落とした後、溶けてしまうので
口に残ることもなく、快適です。
半年に一回の定期健診だった患者様も
その間に1回もしくは2回とか
パウダークリーニングを入れるのも
いいかもしれません。