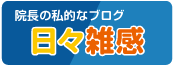前歯の歯並び
一般的な傾向として年齢とともに
歯並びは変わってきます。
加齢とともに
人の骨格自体が変わってくるのと、
歯も全体に前方に傾斜してくる傾向があり、
その結果、歯並びが変わってきます。
よくあるのは
下の前歯の歯並びが
ガタガタになってくる
昔はこうじゃなかったのに、
と良く聞きます
ガタガタしてくると
見た目の問題だけでなく
食物が詰まりやすくなったり
歯垢や歯石が溜まりやすくなったりします。
状況にもよりますが
この歯列不正は
矯正治療で治すことができます。
歯並びの悪化は
年齢とともに進みますので、
できればあまり進まないうちに
矯正することが理想です。
昔は矯正と言うと
歯にワイヤーをつけたりして
ちょっと心理的にハードルが高かったのですが
今は透明のマウスピースで
ほとんど気づかれずに
矯正が可能です。
歯並びを3Dスキャンし
画面上でお顔と矯正後の歯並びを
シミュレーションし
それを見て、治療するかどうかを
決めることができます。
以前は私も
ワイヤー矯正をさせていただいていたのですが
今はワイヤーで治療することは
まずなくなりました。
前歯がガタガタしてきたら、
早めにご相談くださると
よろしいかと思います。
ただし、
加齢による骨密度の低下に対して
骨粗しょう症の治療薬をご使用の場合
矯正治療時の歯の移動速度が著しく遅くなることが
知られており、
できれば
そのような薬剤を使用する前に
矯正治療をなさることをお薦めします、
もし矯正治療が
現実的に困難だったとしても
ホワイトニングや
パウダークリーニング、
古い詰め物やかぶせ物のやり直しなどで
見た目は大幅に改善可能ですので
一度ご相談くださればと思います。