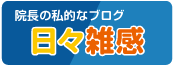「腰眼(ようがん)について」
歯科医はある程度の年齢になると腰痛が持病という人が多くなります。
体をねじって患者さんの口の中を見たり、治療したり
する事が多いからだと思います。
私はおかげさまで
腰痛は無いです。
たぶん診療の時に
体をねじらないからだと思います。
来院されている方はご存知の通り
私はほとんど顕微鏡を使って治療しますので
ねじる必要も、覗き込む必要も無いからです。
まっすぐ座って
前を見ると
目の前に治療する歯がくっきり見える、
本当に歯科用顕微鏡を導入して
良かったと思います。
あとは普段から
正座とか
座る練習をしているのも
関係あると思います。
合気道の時に
正しい正座とか
立ちかた座りかたも練習します。
正しい座りかたをしていると
押されてもバランスが崩れず、
股関節に重心が乗っているので
自在に動く事が出来ます。
冬に1時間正座をする行をやりますが、
それをするとちょっと正座がわかる気がします。
背骨の両脇の、腸骨の縁に
腰眼、というつぼがありますが、
正座の時にはその腰眼をきゅっと立て
股関節の中心に重心をのせ、
上半身は肩肘張らず
ふわりと腿のうえに手を置く。
肩肘はって胸を張りすぎると
対面する相手に威圧感を与えます。
そもそも相手に威圧感を与えてしまうのは
合気道のコンセプトから外れてしまいます。
安定した感じ、そして力の抜けた感じ
そのポイントは
腰眼にありそうです。
練習の時に袴をはきますが
袴には背当て、というのがあります。
腰眼を守り、腰眼を鍛える
らしいです。
座りかたを学んだ事で
最近寿司屋のカウンターとかでも
何となく違和感無く
座れるようになってきました 笑
まだそんなに居心地が良いわけでは
ないですが
顕微鏡とか合気道とか
いろいろな事が
おかげさまで
いいタイミングで
めぐりあわせている感じがしています。