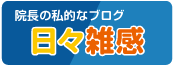明るく楽しく
老人保健施設、いわゆる老健は
介護保険の給付対象施設であり
自宅で生活が困難になった高齢者が
リハビリを行いながら生活し
自宅復帰を目指す施設です。
私の母も老健に入っていました。
そこの施設はグループの理事長が
私の父方の親戚で
とても良くしてもらったのですが、
大きな施設は
今はコロナで
面会が大変
できても予約制、パーテーション越し、
15分までという
外泊もできない、ということで
どうしたものかと思っていたら
申し込んでいたグループホームが
空きが出たとのことで
引っ越しました
ちなみにグループホームは
介護保険の給付対象施設で
認知症患者さんたちが
協力しながら生活します
母の入ったグループホームは
家の近所ですが
周りは田んぼや梨畑に囲まれていて
どこか両親の故郷の鳥取に似ているような
そこは面会も外泊も自由で
車いすで外の散歩もできる
引っ越しの日は
私の父と私の子と私で母を連れて引っ越ししました。
部屋で子供が母の痛む足を揉んであげていて
その後、介護士さんがきて母はダイニングにおやつに行き
「これ美味しいわ、とってもおいしい」
という母の元気な声が聞こえ
ちょっと安心して私たちは家に帰りましたが
その声が最後に聞いた母の声になりました
次の日曜日は
母を車いすに乗せて
皆で散歩しよう、などと思っていたら
今度は父が腰椎の圧迫骨折でどうにも動けなくなり
東京消防庁のHPでは
65歳以上で急な腰痛で動けないときは
救急車を呼んでとありますので
救急車で、入院となり
バタバタして日曜日が終わってしまい
グループホームから電話があったのは
次の月曜日の早朝でした
救急隊からで
母が心肺停止している
延命処置をしますか?とのこと
90歳、長く認知症と足の神経痛を患いながらも
直前まで元気で
寝ている間に
スッと亡くなったのです
「しなくていいです」と伝えました。
救急隊の方は「わかりました」とのこと
一応決まりなので、心臓マッサージはしますとの事でした
そう答えた理由はもう一つありました
母のその母も認知症でした。
鳥取で、さらに今のような介護サービスもなく
周りの人はすごく大変で
その様子を見ていた母は
私がボケてしまったら死なせてくれと、
よく言っていました。
そして6年前のことでした。
自宅で母の認知症が進んで
水道の蛇口も止められない
時々おかしなことをしてしまうようになり
困った父が私に「どうする」と
いろいろ相談していて
その数時間後
母は心筋梗塞で倒れました
いろいろあっても
まだ母は元気でしたし
短期記憶はなくても
瞬時の判断力とか言うことはシャープで
私は迷うことなく
心臓マッサージをして
救急隊に引き継ぎました
その数日後、生還した母に
病室でそのことを話すと
「あら、生き残っちゃったのね」と
言っていたのでした。
あれから何度も正月を家族で過ごしました。
ある正月には母は俳句を一句作りました。
「ふるさとの 海鳴り聞こゆ 初電話」
いろいろありましたが、
明るく楽しく、
よく生きてくれたと
思います。