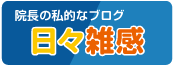試し行動
「試し行動」とは子供などが
親が困るのをわかっていて
わざと悪さをして
反応をうかがうものです。
どこまで、どのように受け入れてくれるか、
を試しているのです。
根底には
不安、喪失感などがあります。
あと愛情を感じるのに苦労する
発達障害なども
下の兄弟ができて
愛情が失われたと思い
赤ちゃん返りしたりするのも
試し行動
里子になったり
親の離婚などで
大変な喪失感を感じた子供は
はじめはよく思ってもらおうと
すごくいい子にふるまうのですが、
その後、試し行動に出ます。
相手がキレて
関係を解消するかどうかを
試す
こういう子供の態度を受け入れる大人には
相当な包容力が必要とされますが
残念ながら、虐待などが起きたりすることも
あるのかもしれません。
これは実は大人になっても
続きます
根底にあるのは
不安感
孤独感
自己肯定感の低さ
各種障害
など
愛着障害、とも呼ばれるようです。
はじめはすごく感じがよかったりします。
でも
信用してから
そのあとに深く傷つくくらいなら
その前に
関係を拒絶したり
自ら関係を壊してしまう
時に石橋をたたいで壊す、
みたいなことを
繰り返してしまう。
これは
歯科恐怖症の患者さんでも起こります。
歯の治療で以前にすごい大変な思いをしたりしていると
その後
親切そうな歯科医に出会うと
非現実的な要求をしたり
すごい質問攻めにしたり
あれはするな、これもするな、
私は~治療はダメなんです、
ネットではこう書いてあったのになぜ、
悪徳なんじゃないか、とか
こちらの対応としては
もちろん緊急性の高いところは優先的に治療しますが、
残りについては、ハードルの低いところから治療させていただいて
だんだん、慣れてもらいます。
なんだ、こんなもんか、
と思ってもらえればしめたものです。
説明にも、治療にも
時間がかかりますし
様々な配慮が必要ですので
正直、安い費用でできる治療ではありません。
もちろん、先に治療計画書で金額はお伝えしてから
はじめます。
しかしそこで
少しでも治療結果に
気になることがあったりすると
それ見たことか、どうしてくれるのか、
あなた「も」ひどい人だ、
みたいな話になりやすいです。
歯科の治療は確かにミクロン単位ですが
結局人がすることですので
その後に生体が適応してくれる部分が
大きいです。
症状がなくなるまで
時間がかかることもありますが
生体の適応能力は
極めて高いものです。
しかしそれが待てない
根底には不安感があり
先の見えない状況でも
何となく楽観視して待つという
以前書いた
「ネガティブ・ケイパビリティ―」が
不足しています。
こうなりやすいのは
例えば前の先生をすごく信用していたのに
トラブルになってしまったとか、
親御さんなどが
口腔がんで亡くなったり、
亡くなりかけたとか、
それから、
トラブルになる前に
治療した先生が
実は親だったり、
親しい親戚、
つまり根本的に信頼していた人だったりすると
さらに厄介なことになりやすいです。
お気の毒ながら、そのような方が
まれにいらっしゃいます。
私も気を付けないと
その対応で感情的になってしまいそうに
なることもあり
まだまだ修行が必要そうです。